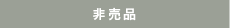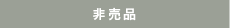主要統計
◎Report
大規模商業店舗立地の変化と商業空白地へのアプローチ
◎ワンポイント解説
都市圏の減少と変質するベッドタウン
【Report】大規模商業店舗立地の変化と商業空白地へのアプローチ
|
|
流通業では、従来の低価格志向は続きながらも、身近で安心して買物ができる場所への志向が高まり、店舗網が細かく広いコンビニエンスストアがその強みを発揮し新たな成長段階に入っている。近年の小売店の立地動向の変化を整理するとともに、商業空白地に対応した移動販売等、新たなビジネスの可能性について考察した。
|
-
流通業の多くが 「小商圏対応」を志向。DS、DgSでは食品・生鮮品を強化し成長。CVSの競争力も増し、スーパーの売上に近付く。
-
消費者のニーズに対応して、商業空白地にアプローチする移動販売、宅配ビジネス。
-
ファミリーマートの移動販売車「ファミマ号」、長崎市神ノ島工業団地内に開業。顧客は順調に定着し、現在は当初の目標通りの売上達成。通常店舗のサテライト機能に。
-
グリーンコープふくおか「みんなのお店元気カー」、高齢化するニュータウン等の買物弱者の増加に対応。販売車では約200アイテムを販売。コミュニティ内の交流を促す役割も果たす。
-
高齢者向け弁当宅配サービスを行うシニアライフクリエイト(東京都)、CVSと組んで「買物お助け便」を開始。宅食サービスに小売業販売を組み込み、収益性を高める。
|
 |
【One Point】 都市圏の減少と変質するベッドタウン
|
-
2010年の国勢調査より、通勤依存度10%以上の九州・山口の都市圏を分析。2010年は32都市圏と、05年の35都市圏から3つ減少。
-
2010年には就業者数の減少が加速。団塊の世代が退職しはじめたことが主因。
-
縮小局面にある都市圏が多数。一方福岡市・那覇市都市圏では、周辺部で雇用を吸収する「職住近接型」のベッドタウンも。郊外型小売店が若年雇用の受け皿になる動きがみられる。
|