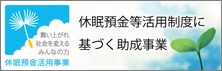2009年7月号

A4版・64頁
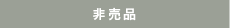
2009年7月号
◎論文・レポート
九州の森林資源の可能性 ~新しい需要と価値創造~
博多港を基点とする国際シーアンドレールの現状と課題
福岡市における屋台に関する市民意識の変化
~過去のアンケート調査結果との比較を中心に~
◎ワンポイント解説
低水準にとどまる電子マネー利用
内容
九州の森林資源の可能性 ~新しい需要と価値創造~
九州は全国に比べ森林に占める人工林の割合が多い。近年、それらが収穫の時期を迎えたことや、合板用、製材用素材需要の高まりから、九州の素材生産量は 増加傾向にある。国産材の需要は、林野庁が主導し、製材・合板メーカーで国産材を使った製品開発を進めたことや、外材に依存した事業のリスクをヘッジする 民間企業の意識変化などを背景に増加している。また、豊富な森林資源は、木質バイオマスとしてのエネルギー利用や排出権クレジットとしての利用、ナノカー ボン素材への利用等、多くの可能性を秘めており、一部は実現に至っているものもある。今後は、森林施業、伐採、搬送に係るコスト問題の解消など、新たな需 要によって生み出される資金を山主まで環流させる仕組みづくりが必要である。
博多港を基点とする国際シーアンドレールの現状と課題
国際シーアンドレールとは、船と鉄道が連携する国際複合一貫輸送システムである。東アジアと地理的に近い九州では、博多港を基点とした国際シーアンド レールシステムが構築されており、博多-上海間の高速RORO船や下関-釜山、博多-釜山間のフェリー等の定時制の高い輸送モードが、同システムの正確性 とスピードの鍵となっている。ただし、ポテンシャルの高さに比して企業の導入は十分に進んでいない。利用を増やすためには、鉄道から船への積み替え時のコ スト・リードタイム削減や手続きの簡素化、海上輸送に係るバックアップ体制等の課題を、国境・業界の垣根を越えた連携・協力によって解決する必要がある。
福岡市における屋台に関する市民意識の変化
福岡市を代表する観光資源のひとつである「屋台」についてアンケート調査を行ったところ、福岡市民の屋台の利用頻度は減少しているものの、市民は屋台の 営業スタイルや雰囲気に魅力を感じており、今後も存続を希望する意見が高まっていることがわかった。一方、公衆衛生面が課題と考える市民も多く、屋台経営 者の後継者難などを含め、課題も残されている。
ワンポイント解説 低水準にとどまる電子マネー利用
総務省「家計消費状況調査」によると、九州におけるプリペイド式電子マネーの世帯保有率は11.3%、利用率は6.4%であり、全国の保有率 24.4%、利用率18.0%に比べ低いことがわかった。利用率が高いのは首都圏であり、交通系カードの普及率の高さが電子マネーの利用を増加させてい る。九州においても、2008~09年にかけて交通系カードのサービスが開始されているため、今後は利用が進むと考えられる。