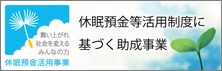2008年10月号

A4版・54頁
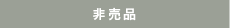
2008年10月号
◎論文・レポート
拡がりをみせ始める九州の陸上養殖
公共交通空白地域における新たな地域公共交通の展開
◎ワンポイント解説 非正規就業者の増加で伸びる正社員の就労時間
内容
拡がりをみせ始める九州の陸上養殖
海産魚類を対象とした陸上養殖が、九州各地で拡がりをみせ始めている。九州は他地域に先駆けて陸上養殖を大規模化してきたことから、養殖ヒラメの生産 では大分県が全国の約3割を占めており、トラフグについては長崎県のシェアが5割を超えている。陸上養殖は、種苗技術の確立により通年での市場供給が可能 になったこと、多くの生けすを所有していれば出荷日を逆算して供給量の調整が可能であることなどから、市場動向に柔軟に対応できるメリットがある。一方、 課題としては、原油価格高騰による資材価格やランニングコストの増加、世界的な漁食ブームによる飼料価格の高騰など生産コストが上昇していることである。 単価については、ヒラメは上昇傾向にあるものの、トラフグについては中国産フグの輸入増加により低下している。このように業界を取り巻く環境は厳しくなる 中、中小零細事業者が多い九州では、事業者としてまとまることで流通業者への発言力を高めつつ、ブランド化などで直取引を拡大させる必要がある。また、産 業振興の面から、行政が何らかの支援を行うことも必要である。
公共交通空白地域における新たな地域公共交通の展開
公共交通空白地域とは、徒歩で移動できる距離に駅やバス停など公共交通手段が無い地域のことである。自家用車の普及と赤字バス路線の廃止によって、公共 交通空白地域は拡大しつつある。空白地対策として、地方自治体ではコミュニティバスや乗合タクシーの導入を進めているが、住民の関心の低さや、既存バス路 線との整合性が考慮されていないことなどから、利用者が極端に少ないものが多く、また、収入不足を財政補填に頼っており、萎縮する地方財政にあって、今後 運行が難しくなるものが多くなると考えられる。北九州市枝光地区や長崎県五島市福江地区では、行政の補助金に依存しない、新たな地域公共交通の試みが進め られている。この2つの地域の特徴としては、住民や自治体が地域公共交通の運営に積極的に関与し、住民の利用促進を図ると共に、協賛金集めなどで収入不足 を補っている。このような新たな地域公共交通を広めていくためには、既存の公共交通機関との乗り継ぎの利便性を向上させ、利用者を増加させることなどが求 められる。
ワンポイント解説 非正規就業者の増加で伸びる正社員の就労時間
九州の雇用形態別雇用者をみると、2002年から07年にかけて、正規就業者(正社員)は1.3%減少したのに対し、非正規就業者は19.1%増と大幅 に増加した。雇用者に占める非正規就業者の割合は、2002年の34.6%から、2007年では39.6%まで高まっている。このような中、正規就業者の 残業は以前よりも増加し、就業時間の長時間化が進んでいる。週60時間以上働いている男性正社員の割合は、2002年の17.0%から07年では 18.4%に伸び、女子正社員でも02年の5.2%から07年では7.2%に増えている。