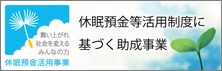2008年3月号

A4版・62頁
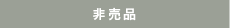
2008年3月号
◎論文・レポート
イタリアの地方分権と地域振興
◎新・景気指標を読む
業況判断調査からサービス消費の動向をみる
◎ワンポイント解説
東海圏企業の支店が急増する九州・山口の事業所
内容
イタリアの地方分権と地域振興
本稿は、地方分権と地方振興をテーマに行ったイタリア視察の報告である。
イタリアにおける1970年代以降の地方分権の流れの中、エミリア・ロマーニャ州では、人材育成や起業支援、産学連携による研究開発機能の強 化等、地域に密着した振興策が講じられた結果、90年代まで高い経済成長を達成し、「エミリアモデル」として世界的な評価を得た。90年代以降、高度人材 の域外流出や産業育成等における域内連携の絆のゆるみ、サービス経済化への対応不足等から地域経済が停滞したものの、2004年以降は地域結束の再強化を 図り、かつてのエミリアモデルを進化させた取組を行っている。
一方、南部地域においては、国家主導による重化学工業振興等が2度のオイルショックで頓挫し、経済が停滞した。地域の行政や労働組合が主体と なる「下からの開発」により、一定の域内外の投資を呼び込んだものの、地域が有機的に連携した振興策をとれなかったため、活性化策が長続きせず、再び停滞 している。
九州においても、道州制の到来に向け、エミリアモデルの成功と南部地域の停滞のキーワードとなった「濃密な地域連携」を重視したインフラ整備や人材育成、産業振興を行う必要がある。
新・景気指標を読む『業況判断調査からサービス消費の動向をみる』
個人消費をみる上で、サービス消費の把握の重要性が高まっているが、地域のサービス消費をみる指標が一部に限られるため、動向把握も困難である。そこで、 これまであまり注目されてこなかった日銀短観と小企業動向調査におけるサービス業の指標から、地域のサービス消費の動向を考察した。同指標によると、 2005年後半から07年前半にかけてサービス消費は個人消費を下支えしたが、07年後半以降はサービス業の業況も悪化しており、足許のモノ・サービスの 消費に不透明感が漂っている。
ワンポイント解説 東海圏企業の支店が急増する九州・山口の事業所
九州における事業所数、従業者数の推移をみると、1996~2006年の10年間で事業所数は2,163増加したが、従業者数は189,930人減少し た。本社・支店別では、事業所数、従業者数とも単独事業所と本社が減少するなか、支店は増加している。支店の従業者数を本社所在地別にみると、東京圏、近 畿圏を本社とする支店従業者が減少する一方、東海圏を本社とする支店従業者は大幅に増加している。自動車産業を中心とする企業進出が背景にある。