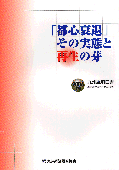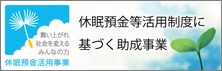|
目 次 |
|
序章 |
都心をとりまく環境変化 |
|
1章 |
変調をきたす地方中枢・中核都市の都心 |
|
2章 |
衰退する地方中小都市の都心 |
|
3章 |
都心の新たな可能性 |
|
4章 |
都心再生に向けて |
|
|
|
概 要 |
|
1章 |
変調をきたす地方中枢・中核都市の都心 |
|
1 |
都心の拡大力と求心力の変化 |
|
● |
都市圏の周辺地域と中心都市の人口増減率逆転→拡大力に翳り |
|
● |
求心力(都心の吸引力)…都心流入者の減少で求心力低下 |
|
2 |
集客力低下する都心の小売機 |
|
2章 |
衰退する地方中小都市の都心 |
|
● |
停滞する都市…中小都市では中心都市、都市圏ともに人口減少 |
|
● |
都心小売機能の衰退 |
|
● |
集積が弱まるオフィス機能 |
|
3章 |
都心の新たな可能性 |
|
1 |
都心の成長産業の概況 |
|
● |
サービス業が都心の空洞化を抑止 |
|
● |
個人向けサービス業(福祉健康、教育等)と情報ネットワーク活用産業の成長 |
|
2 |
個人向けサービス業 |
|
● |
個人向けサービス流入の実態 |
|
|
・ 閉鎖小売店舗とオフィスビルへ個人向けサービスが浸透 |
|
|
・ 衰退する中小都市でもサービス業は健闘 |
|
● |
新たな福祉・健康サービスの都心志向 |
|
|
・ 都心立地の営利法人訪問介護、認可外保育施設、各種療法 |
|
● |
教育・学習支援サービスの都心集中 |
|
● |
個人向けサービス業が都心に集まる理由 |
|
|
・ 財に比べたサービスの成長、ビルの空室発生で都心流入が可能に |
|
|
・ 荷物不要、目的の明確な消費、繰返し・時間消費、固定費比率の高さ |
|
|
・ 規制緩和・市場化がサービスの都心立地を促進 |
|
3 |
情報ネットワーク活用産業 |
|
● |
都心に集中するコールセンター |
|
|
・ 福岡市集中から地方中核都市への展開始まる |
|
|
・ 都心のコールセンターが2001年以降、1.6万人の雇用を創出 |
|
|
・ 都心集中の理由…従業員の安定確保と、条件を満たすオフィスビルの都心立地 |
|
● |
ソフトウェア業…福岡市では博多駅から周辺部へ、地方中核都市郊外化、地方中小都市減少 |
|
● |
インターネット関連産業…1各都市に分散2福岡市・中小都市都心集中⇔地方中核都市郊外 |
|
4 |
都心のインキュベーション機能の重要性増大 |
|
● |
起業の都心比率…高まる新規開業率の高さ、SOHOやNPO法人も都心志向 |
|
● |
起業の都心集中が進む理由 |
|
|
・ 都心での官民のオフィス向けインキュベーション施設の充実 |
|
|
・ 路地のリノベーション建築物が若者のショップ経営の受け皿に |
|
|
・ チャレンジショップ事業が、ショップ開業を促進 |
|
5 |
人口の都心回帰 |
|
● |
福岡市、地方中核都市では本格的な都心回帰、中小都市は減少率の下げ止まり |
|
● |
誰が回帰しているのか |
|
|
・ 福岡市…20代中心・一部ファミリー層、熊本市…ファミリー層 |
|
|
・ 地方中小都市(大牟田市・周南市)…ファミリー層に都心回帰の気配 |
|
● |
都心のどこで増えているか |
|
|
・ 福岡市…都心一等地周辺 |
|
|
・ 地方中核都市…都心一等地 |
|
4章 |
都心再生に向けて |
|
● |
都心の現状のまとめ |
|
|
・ 福岡市…既存の都心機能は比較的堅調(小売業は不透明感あり)、新たな芽も育つ |
|
|
・ 地方中核都市…既存の都心機能低迷、新たな芽は着実に育つ |
|
|
・ 地方中小都市…既存の都心機能衰退、力強さに欠けるが新たな芽が生まれつつある |
|
● |
既存機能だけでは都心の再生は困難。まちづくり3法の改正も効果は小さい |
|
● |
都心に求められる新たな役割 |
|
|
・ 生活空間としての都心…高齢化対応+子育て世代、職住一体型ワークスタイル |
|
|
・ 知識社会に相応しいベーシック産業の育成…消費する場から生産する場としての都心 |
|
|
・ 起業家の育成・輩出の場としての都心 |
|
|
・ 人のつながりを提供する場としての都心…都心・郊外の逆転 |
|
|
・ 都心の捉え方の拡大…商業・賑わい空間+α=都心再生の参加者と空間設定の拡大 |