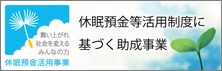2008年6月号

A4版・58
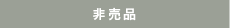
2008年6月号
◎論文・レポート
九州における博物館関連産業の実態と課題
都市における屋台の機能とその変化
◎シリーズ 新・景気指標を読む
新聞折込広告から景気動向を探る
◎ワンポイント解説
観光型施設の宿泊が中心の外国人旅行者
内容
九州における博物館関連産業の実態と課題
九州には563館(2005年)と全国の約1割に当たる博物館が立地しており、市町村設置によるものが71.4%を占めている。全国的に見ると博物館の 総数は増加しているが、1館当りの入館者数は減少傾向にある。入館料収入が減少するなかで、博物館が収入の半分以上を頼る自治体予算も財政難などで減少傾 向にある。
施設管理や資料管理など博物館に関わる産業を「博物館関連産業」と捉えると、九州の博物館関連業務の市場規模は約66億円程度と推測される。そ の主なものが館内環境保全業務と修理修復業務である。九州の博物館では8割以上が何らかの業務を外注しており、警備や清掃といった館内環境保全業務では、 九州でも地場企業の参入が進んでいるが、修理修復業務では、人材不足もあり、あまり地場企業の参入は進んでいない。
今後の九州における博物館関連産業の発展に向けた課題としては、博物館による収入拡大への努力、企業PRの場としての博物館の活用促進、博物館業務への関心の向上、人材育成と市場拡大への試みなどがある。
都市における屋台の機能とその変化
屋台は設置場所(道路等の公有地/民有地)と設置期間(常設/臨時)によって分類でき、従来からの公有地・常設の屋台に対し、最近では民有地に常設され た屋台(村)や駐車場で営業するネオ屋台等が注目されている。公有地にある屋台は、保健所に加え、警察署と道路・公園等の管理者である自治体の占有許可が 必要となり、衛生面だけでなく、交通面や公有地を使用する地代の面からも問題が指摘されている。屋台は歴史的にも「存続か」「廃止か」を巡って議論がくり 返されてきた。日本の多くの都市で屋台が消滅する一方で、福岡市では適正指導による存続の方針を取っており、現在では多くの観光客を引きつける要因となっ ている。しかし、許可権利譲渡が禁止されていることから、近年、事業者の高齢化などから減少が進みつつある。
最近では、全国的に都心に賑わいを取り戻す手段・集客装置として屋台を復活・再生させようとする動きがみられる。屋台(村)を設置している帯広 市や業者数を限定して復活させている呉市のほか、仙台市や北九州市でも復活・再生の検討が行われている。今後は、街の賑わいを創出するための公共空間の有 効的活用の側面から屋台を検討していくことが望まれる。
ワンポイント解説 観光型施設の宿泊が中心の外国人旅行者
2007年から行われている全国統一基準による宿泊旅行統計調査によると、九州7県の延べ宿泊者数は全国の10.8%を占める3,297万人であった。 観光型施設とビジネス型施設でみると九州7県では観光型施設の宿泊者が全体の5割を占め、大分県、熊本県、長崎県では6割以上となる一方、福岡県ではビジ ネス型が7割強を占めた。九州7県の外国人宿泊者数は205万人で全宿泊者に占める割合は6.2%となっているが、佐賀県、宮崎県、鹿児島県では2~3% 程度にとどまっており、国内客が中心となっている。また、国籍別にみると、九州7県では韓国が60.4%と最も多く、全国の20.1%を大きく上回ってい る。