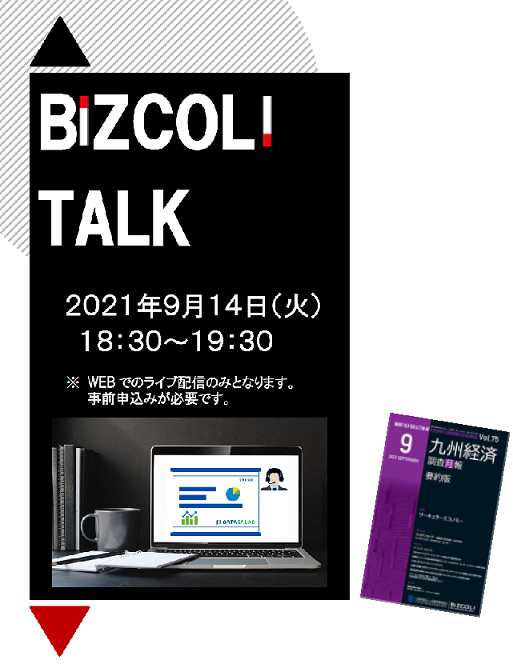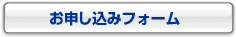|
イライラすることが増えていませんか? 新しい生活様式、働き方、価値観と言ったコロナ禍への対応で、メンタルや思考パターンにも大きな影響を及ぼしています。 アンガーマネジメントとは、「怒る必要のあることを上手に怒るようになること」「怒る必要がないことは怒らない」というための心理トレーニングの一つです。怒りで自分が壊れないために、心の筋力トレーニングを習慣化し、怒りを上手にコントロールして、自分も他人もストレスが溜まらない円滑な人間関係でこの難局を乗り切りましょう! 本セミナーでは、アンガーマネジメントトレーナーの丸山啓太氏に「怒り」の発生メカニズムを踏まえ、このニューノーマル時代に生まれた「新たな怒り」へのコントロール術をお話しいただきます。 |
開催概要
日 時
2021年9月29日(水)18:30~19:30
※ZOOMによるWEB限定のセミナーとなります。
講 師
丸山 啓太 氏 (マルプロ 代表)
|
|
福岡市出身。2000年株式会社リクルート入社。主に人材サービス事業に携わり、2016年独立し、マルプロを設立。アンガーマネジメント、アサーティブコミュニケーション講師として、企業・病院・介護施設・行政機関・部活動など幅広い分野で研修・講演を行っている。 |
参加費
賛助・BIZCOLI 会員:無料
一般:1,000円(WEBセミナー参加の方のお支払い方法は、クレジット決済のみとなっています)
(注:クレジット決済後のキャンセルによる返金はできかねますので、 予めご了承願います。※セミナー中止の場合を除く)
定 員
50名
締 切
2021年9月28日(火)13:00迄にお申し込み下さい ※事前のお申し込みが必要です
ご参加について
★ 参加方法はをご覧ください。
★ 参加までの流れ
①登録完了メール(承認後送信)※登録完了メールが届かない場合はご連絡ください。
②開催1時間前のリマインダーメール ※資料のURLをご確認ください。
③開催日:参加URL、またはID・パスワードにてアクセス
主 催
公益財団法人九州経済調査協会
お申し込みに関するお問い合わせ
公益財団法人 九州経済調査協会 BIZCOLI (担当:牟田・平田)
福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館3F
TEL:092-721-4909 E-mail:bizcoli@kerc.or.jp
備 考
ZOOMによるWEB限定のセミナーとなります。インターネットを通じて開催します。
BIZCOLIが会場ではございませんのでご注意ください。
ご参加にあたっては、登録後に送られてくる参加URLが必要です。